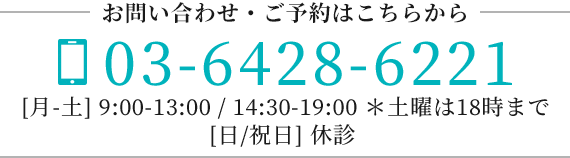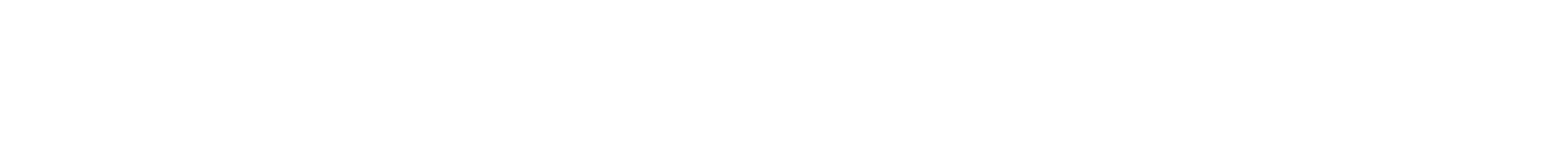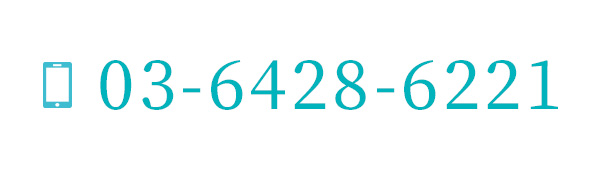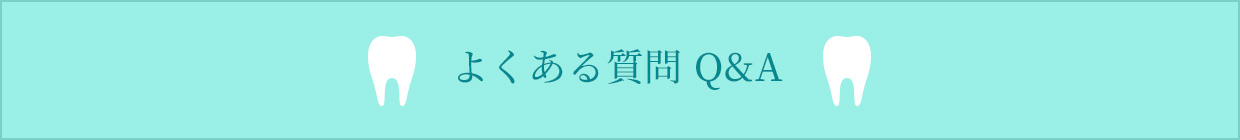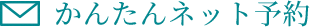皆さん、こんにちは!
JR蒲田駅東口徒歩1分の蒲田駅前歯科・矯正歯科です。
当法人の歯科衛生士の上杉が指しゃぶりについて、お伝えします!
早速ですがパパママの皆さん、お子さんのおしゃぶりについて気になったことはありますか?

指しゃぶりは、哺乳瓶やおっぱいを飲む練習として、お腹にいるころから始まっていることもあります。
生まれた後の指しゃぶりは、不安やストレスから逃れ安心を得るために大切な行動です。
しかし、いつ頃までしているのか、また続くとどんな影響があるのか、長く続いた時の対策はご存知ですか?
今回は、指しゃぶりはいつまでしていいのか、指しゃぶりが続くとどんな影響があるのか、指しゃぶりをやめさせる方法などをお伝えしていきます。
目次
〈指しゃぶりをやめる時期〉
大体、3歳前までに完全にやめることか勧められています。
発育、環境、性格が異なるため一概には言えませんが、一般的に3歳頃までに乳歯が並び終わります。
それ以降でも指しゃぶりを続けていると、歯並びなどに大きく影響しやすくなると言われるため、この年齢くらいを目処にやめさせることが望まれます。
〈指しゃぶりの影響〉
【1 開咬】
前歯に上下方向の隙間ができることを言い、オープンバイトとも言われています。指で歯を押してしまい、歯の軸が変わっていくことで隙間ができてしまいます。
【2 反対咬合】
いわゆる受け口のような状態です。
人差し指や中指を吸うことで下の前歯が前方に出ます。本来は上の前歯が出て、下前歯が下がっている状態ですが、それが反対になってしまいます。
【3 上顎前突】
上の前歯が出過ぎてしまうことです。親指で上の前歯を前に押す力が強いと起きてしまいます。
指しゃぶりの中で最も起きやすい影響の一つです。
【4 歯列弓狭窄】
指を吸う力が強いと、頬の内側に圧がかかり、歯列の幅が狭まります。歯が横に広がって欲しいのに、それが不可能になり、歯が並ぶスペースが減ります。
それによって、歯がガタガタに並ぶことがあります。
また、今お伝えしたこと等が原因で二次的な影響が発生することもしばしば。
歯並びが悪くなったり、開咬によって口がずっと開けっぱなしになったり、舌が下に下がった状態になったり、くちびるを咬む癖がついたり、うまく飲み込むことができなかったり、舌足らずな話し方になったり等。
様々な影響が発生しやすくなります。
〈指しゃぶりをやめさせる方法〉
こういった事にならないように、やめさせる方法をお伝えしていきます。
【1 やめなければいけない理由を説明する】
なぜやめないといけないのか、指を吸うとどんな影響が起こるのか等、お子様に向けてわかりやすく説明します。
絵本のようなお子様向けに作られた指しゃぶりの本もありますので、こんなものを使って説明するといいかもしれませんね。
【2 代替案の検討】

無意識で指しゃぶりをしている場合は、やめなければいけないと説明をしたところで、なかなかやめられません。
そんな時は代替案の検討をする必要があります。
指しゃぶりは、安心したいときにする行為でもあります。そんな時は指しゃぶりではなく、お母さんの手を握るという行為で安心できることもあります。
またお子さんのお気に入りのものをそばに置き、それを握ってもらって気持ちを和らげるような行為も良いですね。
【3 指や口に器具を入れる】
手袋をはめる、マウスピースの装着、爪噛み予防に作られた苦いマニキュアを塗る等、物理的に口腔内に入れられないような器具の装着をするのもやめさせる方法の一つです。
【4 目標達成できた時はご褒美を】
指しゃぶりを我慢できた日は、カレンダーにシールやスタンプを押し、目に見える形で”できた”を表します。
プレゼントを与える等でも良いです。
本人が喜ぶものを与えます。
これは心理学用語でトークンエコノミー法といい、望ましい行動をした時はご褒美を与えるというものです。
これによって、お子様がその行動を頻繁に行える場合があります。

今回は指しゃぶりについてお話しさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか。
もしよければ参考にしてみてください。
またお困りごとがあれば気兼ねなくお尋ねくださいね。
英幸会 歯科衛生士 上杉
【当院についてはこちらから】
【当院へのアクセス】
https://kamata-dental.jp/access/
【小児歯科・小児矯正についてはこちらから】
https://kamata-dental.jp/child/
【ご予約はこちらから】
【予防歯科についてはこちらから】